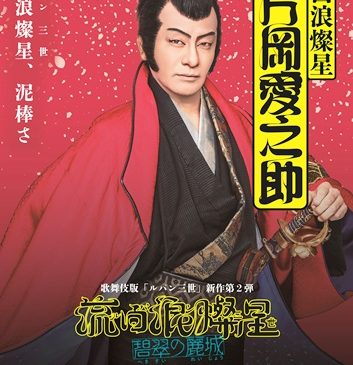2026年2・3月にマキノノゾミの脚本、栗山民也の演出により明治座にて上演される『大地の子』の製作発表が11月27日に都内で行われた。出演する井上芳雄 奈緒 上白石萌歌 山西惇 益岡徹が登壇。作品への思いを述べた。

山西惇 上白石萌歌 井上芳雄 奈緒 益岡徹
原作は 1987 年から「月刊文藝春秋」にて連載され、「白い巨塔」や「沈まぬ太陽」など数々の大作を世に出してきた山崎豊子による同名小説。描かれるのは、中国で戦争孤児となった日本人の少年が、死線をさまよう苦難を経て、中国人教師に拾われ、中国人「陸一心」(ルー・イーシン)として育てられるという、波乱万丈の半生の物語。本作の執筆に際して、山崎豊子は当時外国人に開放されていなかった中国の農村地区に足を運び、多くの戦争孤児から聞き取りを行い、物語に命を吹き込んだ。
1995年にはドラマ化、多くの涙を誘う感動作として、繰り返し再放送されている。

中国の戦争孤児で日本名は松本勝男。7歳で養父・陸徳志にスク(笑)中国人民として育てられた、陸一心(勝男)役
井上芳雄 :このような制作発表はしょっちゅうやらせていただいてはいるんですが、今回、この作品の製作発表は今までにない緊張といいますか、何か大事なものをしっかりお伝えしないと、特にこの作品はそういう見えない重責を感じます。僕自身もドラマで上川隆也さんが一心を演じておられたのを本当に夢中になって見て、そのあと原作も読み返して、僕自身にとってもとても大事な物語だした。その役を演じさせていただけるという、本当に奇跡のような巡り合わせをいただきまして、もうとにかく自分ができることを皆さんと一緒に精一杯やるのみだと思います。なかなか難しい時代になってきておりますし、過去のことを知ることは未来を知ることだと思いますので、それを演劇を通して精一杯お伝えしていきたいと思います。
個人的にはよく「歌わないの?」と言われがちですが、歌いません。ミュージカルではないので。もうミュージカルだとかストレートプレイだとかは、あまり気にしないでやりたいと思っています。

陸一心の実妹で日本名はあつ子。5台で兄と生き別れ孤児となり、中国人の張百案の童養媳(労働力としての将来の嫁)として買われ、過酷な生涯を送る、張玉花(あつ子)役
奈緒:今回のこの大きな物語に参加できることをすごく幸せに感じております。こういった製作発表を舞台でやるということがほぼほぼ初めてでして、こうやって皆さんのお顔を実際に見ていると、この作品の注目度というのを、すごく皆さん期待して待ってくださっているんだなと今この瞬間とても実感しております。
精一杯皆さんと一緒に稽古場でしっかりと自分とも向き合い、物語と向き合い、日々を重ねていきたいと思っています。今日はそんなスタートの日だと思っております。
今回、舞台化にあたって、私がストーリーテラーとなって、妹の目線で描かれるように舞台の脚本が作られています。なので、お客様が私と同じ目線でこの物語をたどってくださることになるのかなと思っているので、そこは自分にとっても今までやったことのない役割で、すごく大きな挑戦だと思ってます。

労働改造所で瀕死だった一心の命を救った看護婦で、後に一心の妻となる江月梅役
上白石萌歌:私もこのような製作発表の場が初めてで、いよいよ始まるんだなという大きな緊張感と高揚感に今包まれているところです。
今年、戦後80年を迎えた今、この作品が上演されること、そして私自身がこの作品に参加させていただけることに、大きな意味を感じております。
今ここに並んで立っていらっしゃる皆様、そして栗山民也さんの言葉を信じて、最後まで自分の役として、こう与えられたものをしっかり噛みしめながら生き抜きたいと思っております。

小学校教師で一心の養父となり我が子同然に育てた陸徳志役
山西惇:この『大地の子』の大役にご指名いただいたということで震えております。とにかく大変な時代になってきているのでね、こういう物語がちゃんと来年の2月、3月にきっちり上演できたら素晴らしいなとは思っています。栗山さんを信じてみんなで作り上げていきたいと思います。

陸一心と張玉花の実父。終戦時に家族全員を失ったと信じて生きてきた松本耕次役
益岡徹:小説として読んでおりますし、30年ほど前にNHKドラマで岡崎栄さんという名監督がお作りになった(脚本が岡崎栄)連続ドラマとして、毎回感動しながら、ひょっとしたら涙を流しながら見てた記憶がございます。そういう世界を今回の舞台で皆さんにお見せできることは、何重の意味でも心震えるような気持ちです。来年稽古が始まりますけれども、その初日までいろんな時間を過ごせるのではないかと思っております。

―プロモーション映像について
井上:今初めて見たんですけど、「あれ?俺中国行っていたかな?」と思いました。ドローンで壮大なスケールで撮っていただきました。半日ぐらいかかって南房総で撮りました。「こんなに時間をかけて撮る必要があるかな」と思ったんですけど、今見たらやっぱり行った甲斐がありました。

―出演決定時、台本を読んだ時の感想は?
井上:原作もドラマも見ていたので、話をいただいた時はびっくりしましたね。好きとかいうレベルではなくて、本当にすごい小説だなと思っていました。舞台で初めてやると聞いて、自分がそこに参加できるなんて信じられないことでしたし、ドラマをリアルタイムで毎週見て家族で毎週泣いていたと思うんですよね。「こんなことがあったんだ」とびっくりしながら、その子供が僕だったらと見ていた覚えがあったので、まず両親に「『大地の子』をやるよ」と知らせましたね。よく言う言葉ですけど、うちの父も「『大地の子』までは元気になるよね」と言っていたので、できれば再演を重ねてずっと元気でいてほしいと思う作品です。両親も喜んでいました。
上白石:山崎豊子さんの本当に大きな壮大な世界に飛び込ませていただくということで、私に務まるだろうかという気持ちがあったんですが、何より私は栗山さんとまたご一緒できるということが本当に楽しみです。栗山さんは私にとっても演劇の神様というか、崇めている存在なので、また栗山さんの言葉をいただきながら稽古ができることが何より楽しみでしたし、姉は井上さんとも何度もご一緒させていただいて、勝手に親戚のように親しく感じています。私が1度ご一緒したのは、たぶん10代。ミュージカル『星の王子さま』でご一緒させていただいたこともありまして、勝手に親戚の心強いお兄さんとまたご一緒させていただけるということもあり、緊張で震えながらも、早くお稽古に入りたいなという気持ちでいっぱいでした。
山西:お話を始めていただいた時は「できんのか?」と思いました。それが最初の印象でした。僕も栗山さんとは10年以上、10本ほど一緒にやらせていただいていて。自分の俳優人生の年表を作ったら、「栗山さんと会う前」「栗山さんと会った後」で紀元前と紀元後の違いほどの信頼を覚えている演出家さんなので、まず栗山さんがやるんだったら絶対大丈夫だろうっていう気持ちと、原作を読み、役柄も「これ、できんのか?」と、まだ思っています。中国の方の役ですけど、僕は中国語は喋らなくていいらしいので、そこのところは安心しました。
その中国語のセリフについては、益岡は「(自分は)数えられるぐらいの中国語のセリフなので、時間をかければ大丈夫だろう。芳雄さんや山西さんは大変だろうな」と話すと「井上が「中国語は基本的に無いと聞いている。僕たちも中国語でとなったら、ちょっとお仕事いくつか飛ばさないと僕も間に合わないかな」、山西は「留学するぐらい(必要)」と、必死に火消に務めた。それでも「大学の第2外国語で中国語を履修した」と言う上白石は、「人名や地名は中国語で発音する場合もあると聞いているので、復習しておこうかと思っている」と話したので、また井上が慌て顔になって、笑いが起きていた。

―若い方に向けて、この作品の魅力をご紹介ください。
井上:本当にまず見て知っていただきたいですし、実話ではないですが、実際あったことをもとにはしています。演劇としてエネルギーのある魅力的なものにしたいと思っています。遠い80年前の話かもしれませんが、個人的には、満蒙開拓団の成り立ちを知れば知るほど、もし自分がその時に生まれていたら、自分もそうだった(残留孤児になった)かもしれないと思います。一心の親子は長野出身という設定ですけど、ほんとに「村々で何十人か(開拓団に)絶対出せ」と言われて、出さないと助成金が下りないというような、今も聞いたことがあるような話もあった。しかも「満州には希望があるんだ」と言われていた。もし今の僕が長野でそういう状況になってしまったら、行く可能性だって結構高いんじゃないかな。例えば、親が「よし行くぞ」と言ったら、子供はついていくしかない。だから、決して「昔って大変だったんだな」というだけの話ではなくて、自分たちの話であるということを、今の僕と同じ世代、もっと若い世代の方たちにも伝えて、そこから何を思うかはそれぞれだと思うんですけど、でも少なくとも同じことは繰り返すべきではないということは共有したいなと思います。
奈緒:今年戦後80年ということで、今年私は戦後80年をテーマにした『WAR BRIDE -アメリカと日本の架け橋 桂子・ハーン-』という舞台作品をやったんですけれど、戦後80年というこの1年と向き合ってきた中で、来年の『大地の子』に向けても、やはり同世代に届けたいという思いは強くありますし、届けるにあたって、あの無知は怖いなと思いながら自分自身が生きていきました。
知らなかったら良かったこともあるのかもしれないと思う瞬間もあったんですけど、今1年向き合ってみて、すごく自分自身が感じているのは、無知というのは余白なのではないか、それは私たち若い世代が持っている大きな強みじゃないかと私自身感じています。
なので、その余白をみんなでどういった優しいもので埋めていくのか。
その選んでいただける1つに、この舞台をしていきたいと思っていますし、みんなで戦後80年という、この戦後という言葉を続けなければいけないと強く感じています。
そのためには、現状で私たちは目の前に戦争があるわけではないので想像し続けることが私たちのこの平和と祈りというのを守り続けるんじゃないかと感じています。皆さんと一緒に祈るような気持ちでこの舞台を共有できたらいいなと感じています。ぜひ劇場に足を運んでいただきたいです。
「今日、これが一番緊張する」と言って井上芳雄が代読した、演出の栗山民也からのメッセージ。
戦争によってかけがえのない命を奪われた人々に、もう一度言葉を送り、全身を与える。
これが演劇の1つの仕事だと、ある劇作家の強靭な姿勢から教えられたことがある。
生者と死者はいつも重なり合う。そのことが私の中に「記憶」という大切な言葉となって強くへばりつき、稽古場でのあらゆる事象と出会うたびに、それが今を映し出す「記憶の再生装置」なのだと考えるようになった。
この山崎豊子さんの「大地の子」を随分と前に読んだ時、広く限りなく拡がる黄色の大地の上を幾万人もの人たちが並んで歩む姿が、生まれては消える影のような運命の残像に見えた。その歴史をどこまでも深掘りした文章の奥には、その時代の陰惨ないくつもの光景が刻まれている。満蒙開拓団のリアルな歴史が、1人の青年を通して明らかにされていくのだが、お国のためという大義のもと、それは国をあげて推し進められた開拓という占領政策であった。そして棄てられていった。
写真と文章で綴る江成常夫さんの「シャオハイの満州」という、旧満州の姿を写し出した記録の本が、私の机の上にある。この物語を考える上で、何度もページを開き、そこに写された残留孤児たちの顔を見つめ、今、何を語りかけようとしているのか。そのぼんやりとどこか漂うような目の奥から、こちらに向かって厳しく無数の感情で問いかけてくる。
―誰も置き去りにしてはいけない。誰もが世界から必要とされているのだからー
そんな死者たちの無数の声が聞こえてくる。
この「シャオハイ」という言葉は、中国語で子供のことである。
稽古に入る時、いつもこんなことから始める。物語に描かれた時代を見つめるため、その時代のその場所の真ん中に自分を立たせてみる。そこで見えてくるもの、聞こえてくるもの、肌で感じるもの、全てを全身で受け止める。時の記憶、場所の記憶を自ら体験してみることから始める。
素敵な俳優たちが揃ったみんなで、この物語をしっかりと丁寧に力を込めて、嘘のない舞台にしたいと思う。
栗山民也

『大地の子』
2026年2月26日(木)~3月17日(火) 明治座
原作 山崎豊子『大地の子』(文春文庫)
脚本 マキノノゾミ
演出 栗山民也
出演 井上芳雄 奈緒 上白石萌歌 山西惇 益岡徹 ほか
公式サイト https://daichinoko-stage.jp/
主催・製作 明治座 東宝